今回は「輪をかけて」という言葉について解説します!
「輪をかけて」とは、と何かと比べてさらに大げさにするという意味の言葉です。

兄は、父に輪をかけて努力家です。みたいに使うよ!
「輪をかけて」とは、一般的な会話の中で使われる言葉で、比較の際によく利用されます。
この記事では「輪をかけて」という言葉の詳しい意味や発祥、使われ方などについても深掘りしています。
興味がある方は記事の続きへどうぞ!
輪をかけてとは?意味は「あるものと比べて、さらに大げさにする」
「輪をかけて」の意味=あるものと比べて、さらに大げさにする
輪をかけてとは、あるものと比べて、さらに大げさにするという意味の言葉です。
人の性格や、状況・状態、などを比較して、なお一層〇〇という使い方をします。
ポジティブにもネガティブにもどちらにも使える言葉ですので、人の性格に対して使う場合は、比較対象になるかたへの配慮も心掛けたほうが賢明です。
また、程度をはなはだしくする、大げさにする、という同じ意味合いを持つ「之繞を掛ける」(しんにゅうをかける)という古い言葉もあります。



比べ方次第で、良いほうにも悪いほうにも使えるんだね!
輪をかけての発祥は「弓道の弦」または「桶や樽を頑丈にまとめている箍」
「輪をかけて」の発祥=弓道の弦(つる)
「輪をかけて」の発祥=桶や樽を頑丈にまとめている箍(たが)
「輪をかけて」という言葉の発祥は諸説ありますが、その中でも二つの説を紹介します。
ひとつ目は、弓道の弦(つる)の張り方だと言われる説です。
弓道で弓に弦(つる)を張る時に、弦の両端に弦輪(つるわ)という輪を作ります。これを弓の上下の端にかけて矢を飛ばせる状態が完成します。
きっちりと弦輪を作り弦をピンと張ることで、より一層、力強く矢を飛ばすことができる様子から起用されていると考えられます。
ふたつ目は、桶(おけ)や樽(たる)をしめている箍(たが)です。
桶(おけ)や樽(たる)は、板材を円形につなぎあわせて、その外側に箍(たが)をはめて作っていきます。
この箍は、桶や樽よりさらに大きい円形になっています。この、より一層大きいという様子から起用されているという説です。



日本の伝統的な技術からきている言葉みたいだね
輪をかけての使い方・例文
「輪をかけて」という言葉を使った例文を見ていきましょう。
使用例①



係長は、とても温厚ですよね。



そうですね。課長も温厚ですが、係長は輪をかけて温厚ですね。
使用例②



来週は寒いらしいですね
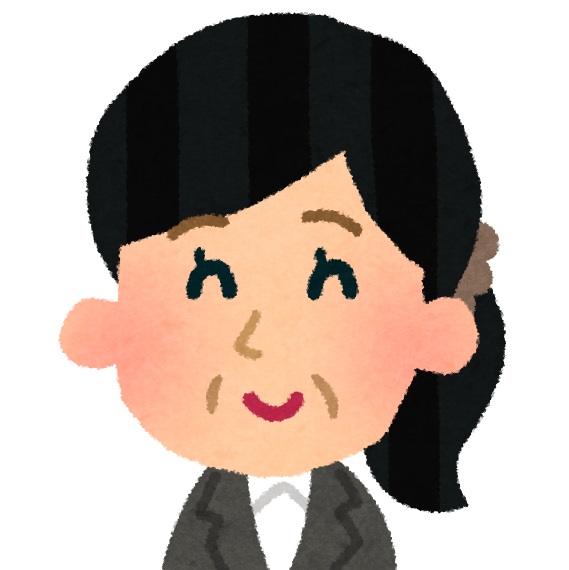
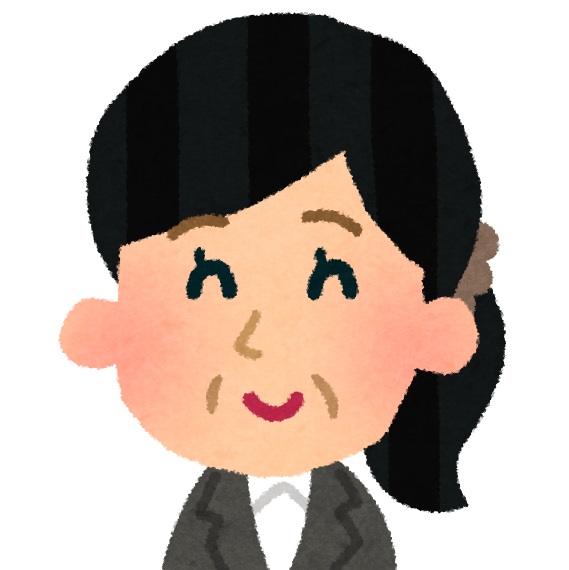
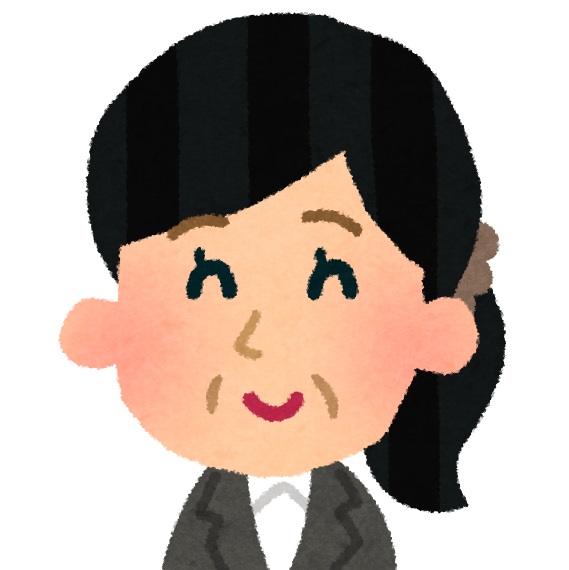
今週の寒さに輪をかけて寒いらしいですよ。
退職や転職で悩んでいるあなたへ
使用例③



そんな話しは、到底賛成できない



やれやれ、お父さんは昔の頑固さに輪をかけて頑固になったなぁ
輪をかけての類義語や対義語
「輪をかけて」の類義語と対義語についても見ていきましょう!
輪をかけての類義語
「輪をかけて」の類義語としては下記のものがあります。
一段と



来週は一段と寒くなるらしいから、気を付けないと。
さらに



父は、以前よりさらに頑固になっていて困るよ
より一層



より一層キレイになったね
輪をかけての対義語
「輪をかけて」の明確な対義語はありません。
退職や転職で悩んでいるあなたへ